ベタニアのマリアは、ヨハネ福音書の中では、変わった女性として描かれている。カナの婚礼の場面でのイエスの母、ヤコブの井戸でのサマリアの女、ベタニアのマルタ、そして、マグダラのマリア、これらの女性たちは、それぞれ個性は違っていても、イエスと対峙しながら、イエスに感化され、隣人にも向かい、「神と人と隣人」の関係をつくるようになっていくのである。ベタニアのマルタは、イエスに導かれて、しまいには使徒ペトロと同じ信仰告白をするところまで高められた*1。マルタはペトロと同じように、御父とつながったのである*2。しかし、ベタニアのマリアは、違っていた。
*1「はい、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子、メシアであるとわたしは信じております」(ヨハネ11,27)
*2「バルヨナ・シモン、あなたは幸いだ。あなたにこのことを現したのは、人間ではなく、天におられる私の父である」(マタイ16,17)
まず、ルカ福音書の場面から見ていく。いろいろなもてなしのためせわしく立ち働いていたマルタが、イエスに、「主よ、姉妹は私だけにおもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください」(ルカ10,40)とダイレクトに言えたことは、すでに二人の間に信頼関係ができていたことを示している。「そばに立って言った」(ルカ10,40)という描写からもそれがよくわかる。また、イエスが「マルタ、マルタ」と彼女の名を2度続けて呼びかけているところからも、それが察せられる。イエスはマルタに、「マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことに気を遣い、思い煩っている。しかし、必要なことは一つだけである。マリアは良いほうを選んだ。それを取り上げてはならない」(ルカ10,41~42)と言った。イエスは、このときマルタにただ一つ必要なことは、マリアの隣人となって、彼女の選択を尊重することだと助言したのである。
このベタニアでの出来事の直前には、「良いサマリア人」のたとえが置かれている(ルカ10,25~37参照)。ここでも、イエスと律法の専門家とのやり取りに、マルタとのやり取りと同じようなテーマを見つけることができる。一つは、彼らが、イエスとある程度良い関係の中で、イエスから会話を引き出していること。そして、イエスが彼らに、彼ら自身が隣人になることについて注目させていることである。
ルカ福音書におけるこれらのテーマは、ベタニアのエピソードを通して、ヨハネ福音書に引き継がれた。イエスがラザロを蘇らせる場面の初めに、ヨハネ福音記者が、「ある病人がいた。マリアとその姉妹マルタの村、ベタニアの出身で、ラザロと言った」(ヨハネ11,1)とマリアの名を先に書いたのは、「このマリアは主に香油を塗り、髪の毛で主の足をぬぐった女である」(ヨハネ11,2)というフレーズを続けるためであった。ヨハネ福音記者が、ここでわざわざ後に書かれるエピソードをもとにこのフレーズを挿入したのは、マリアが、ヨハネ福音書に登場する他の女性たちと違うことの重要性を、あらかじめ強調しておきたかったためである。次に「イエスは、マルタとその姉妹とラザロを愛しておられた」(ヨハネ11,5)と書いてある。マリアの名は書かれていない。ヨハネ福音記者は、ベタニアのマリアに対して、快い印象を持っていなかったようだ。
イエスがベタニアに到着する場面には、「さて、イエスが行って御覧になると、ラザロは墓に葬られて既に四日もたっていた」(ヨハネ11,17)というフレーズが挿入されている。すでにラザロを蘇らせる決心をしていたイエスは、着いたことを知らせて村に入らず、直接墓に案内させるために出迎えを待っていた。神であるからこそ、人の「自由な意思」の決定を知ることのないイエスは、おそらくマルタとマリアがともに迎えに出てくると思っていたにちがいない。
しかし、「マルタは、イエスが来られたと聞いて、迎えに行ったが、マリアは家で座っていた」(ヨハネ11,20)と書かれているように、マリアは、マルタが家に帰ってきて、「先生がいらして、あなたをお呼びです」(ヨハネ11,28)と耳打ちするまでそこに座って待っていたのである。ここでマルタが耳打ちしたとあるので、マルタはマリアを自発的に呼びに来た可能性がある。「あなたをお呼びです」と言う言葉がマルタの“機転”であったので、他の人に聞かれたくなかったのだ。福音書は、マルタがマリアを迎えに行っている間、「イエスはまだ村には入らず、マルタが出迎えた場所におられた」(ヨハネ11,30)と書いている。イエスは、マルタの考えを見通して待っていたのである。マルタは、イエスの助言によって明らかに成長していた。彼女は、マリアの隣人として行動した。マリアの選択を尊重し、イエスとともに「神と人と隣人」の関係をつくっていた。
マルタは現存する神であるイエスを見て、彼の現実に追従する。それは、イエスに導かれて、使徒ペトロと同じ信仰告白をするところまで高められたマルタが、「あなたがたの見ているものを見る目は幸いだ。言っておくが、多くの預言者や王たちは、あなたがたが見ているものを見たかったが、見ることができず、あなたがたが聞いているものを聞きたかったが、聞けなかったのである」(ルカ10,23~24)と言ったイエスの言葉を現実に味わっていたからである。
一方マリアは、マルタの言葉を聞くとすぐに立ち上がり、イエスのもとに行った。さすがに待ちくたびれていたのだ。ラザロは葬られて4日もたっていたので、イエスはまず家に来られると思いこんでいたにちがいない。そこでマリアは家にいてイエスの来訪を座って待っていたのだ。マリアは、イエスの前に着くや否や、「主よ、もしここにいてくださいましたら、わたしの兄弟は死ななかったでしょうに」(ヨハネ11,32)と言った。これはマルタも同じだった(ヨハネ11,21参照)。しかしマリアには、マルタのように「しかし、あなたが神にお願いになることは何でも神はかなえてくださると、わたしは今でも承知しています」(ヨハネ11,22)と言う発想はなかった。それは、「家の中でマリアと一緒にいて、慰めていたユダヤ人たちは、彼女が急に立ち上がって出て行くのを見て、墓に泣きに行くのだろうと思い、後を追った」(ヨハネ11,31)という描写からわかる。マリアは、「慰めていたユダヤ人たち」に慰められ、イエスにも同じ慰めを求めて、急に立ち上がって出て行ったのである。
「イエスは、彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、憤りを覚え、心を騒がせて、言われた。『どこに葬ったのか。』彼らは、『主よ、来て、御覧ください』と言った」(ヨハネ11,33~34)。イエスには、神の計画を成就する日が近づいていた。イエスが聖体制定をし、真の花嫁となる最後の食卓も、翌日妻となる十字架も、すでに彼を待っていた(ヨハネ3,29参照)。今はすべてがその時を目指して加速していることを、イエスは全身で受け止めていた。受難と死は目の前まで迫っている。ラザロを蘇らせ、時宜を推し進めなければならない。
一方でイエスは、ご自分が直接養成してきた弟子であるマリアの状態を見て、深く憐れんで泣いた。ユダヤの民として成長したマリアの善悪の知識は、すでに、神の計画を「蛇」の情報(偶発的情報)とともに、五感データの記憶から、自分の知識として取り込んでいた。しかし、イエスと出会い、イエスが手引きしているにもかかわらず、彼女は神の計画に向くことがなかった。創世記のエバのように、「蛇」の情報(偶発的情報)から、固有のフィクション(虚構)の世界をつくり、そこで生きていたのである(「神学の河口」№14参照)。「イエスは涙を流された。ユダヤ人たちは、『御覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことか』と言った。しかし、『盲人の目を開けたこの人も、ラザロが死なないようにはできなかったのか』と言う者もいた」(ヨハネ11,35~37)。今も、多くの人々がこのように神に問う。やがてこの問いは、イエスが十字架上で聞くことになる侮辱の言葉へと置き替えられていく。
「神殿を壊し、三日で建てる者、神の子なら、自分を救ってみろ。そして十字架から降りて来い」(マタイ27,40)、「他人は救ったのに、自分は救えない。イスラエルの王だ。今すぐ十字架から降りるがいい。そうすれば、信じてやろう」(マタイ27,42)、「彼は神に頼ってきた。お望みならば、神が今、救ってくださるように。『私は神の子だ』と言っていたのだから」(マタイ27,43)「おやおや、神殿を壊し、三日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみろ」(マルコ15,29~30)、「他人は救ったのに、自分は救えないメシア、イスラエルの王、今すぐ十字架から降りるがいい。それを見たら、信じてやろう」(マルコ15,31~32)、「他人を救ったのだ。神のメシアで、選ばれた者なら、自分を救うがよい」(ルカ23,35)、「お前がユダヤ人の王なら、自分を救ってみろ」(ルカ23,37)、「お前はメシアではないか。自分と我々を救ってみろ」(ルカ23,39)。
「イエスは、再び憤りを覚えて、墓に来られた。墓は洞穴で、石で塞がれていた。イエスが、『その石を取りのけなさい』と言われると、死んだラザロの姉妹マルタが、『主よ、もう臭います。四日もたっていますから』と言った」(ヨハネ11,38~39)。マルタはありのままの自分の姿でイエスと関わることを恐れない。自発的にどこまでもイエスの現実、神の現実に追従する。神の計画を目指すこの自発性こそが愛である。この愛はイエスから会話を引き出す。「イエスは、『もし信じるなら、神の栄光を見ると言ったではないか』と言われた」(ヨハネ11,40)。このイエスとマルタの会話の場面は、キリストの聖体とキリスト者の間で、今も繰り返されている。
イエスがラザロを蘇らせる場面の初めに、「このマリアは主に香油を塗り、髪の毛で主の足をぬぐった女である」とあらかじめ強調したヨハネ福音記者は、この後に続くベタニアの夕食の場面でのマリアの行為に注目している(ヨハネ12,1~8参照)。
ベタニアで、人びとは食事をとっていたところであった。マルタは給仕をしていた。そのとき、マリアがナルドの香油を持って来て、イエスの足に塗り、自分の髪でその足をぬぐった。「家は香油の香りでいっぱいになった」とある。人々が食事を楽しんでいる時、その場が香油の香りでいっぱいになることを望むだろうか。マルコ福音書では、食事の席でイエスの頭に香油を注いだ女に向って、ある人々が憤慨して、「何のために香油をこんなに無駄にするのか。この香油は三百デナリオン以上に売って、貧しい人々に施すことができたのに」(マルコ14,4~5)と言った。「そして、彼女を厳しくとがめた」と書いてある。
また、弟子たちは、すでにヨハネ福音書の前の章(ヨハネ11,7~16、46~57)から書かれていることから、イエスが決起するのではないか、というような緊張感を持っていた。そこでこのようなときに、香油を持って来て塗り出した女にいらいらしたかもしれない。またそれを売れば剣の一振りでも買えると考えたのかもしれない。マタイ福音書では、香油をイエスの頭に注いだ女に対して、「弟子たちはこれを見て、憤慨して言った。『何のためにこんな無駄遣いをするのか。高く売って、貧しい人々に施すことができたのに。』」(マタイ26,8~9)と記載されている。これらのことから推測すると、このとき誰も口ほどには貧しい人びとに、関心を持っていなかったと見ることができる。イエスは彼らの心を知っていた。そして、たしなめて言ったのである。「貧しい人々はいつもあなたがたと一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。」(マタイ26,11)。
共観福音書に登場するイエスに香油を注いだ女性たちとの違いから、マリアは、自分だけでイエスと独自のフィクション(虚構)を編んでいたことが分かる。マタイとマルコ福音書の2人の女性は、イエスの頭に香油を注ぎかけて終わる(マタイ26,7、マルコ14,3参照)。ルカ福音書の女性は「罪深い女」で、「後ろからイエスの足もとに近寄り、泣きながらその足を涙でぬらし始め、自分の髪の毛でぬぐい、イエスの足に接吻して香油を塗った」(ルカ7,38)と書いてある。彼女が自分の髪でぬぐったのは、自分の涙であった。ベタニアのマリアは、この3人の誰とも違う特別な行為をした。彼女だけが、香油を「イエスの足に塗り、自分の髪でその足をぬぐった」(ヨハネ12,3)のである。この行為によってマリアは、イエスの足に塗ったナルドの香油の香りを自分の髪にも移した。
マリアも他の弟子たちのように、イエスが今どのような時宜にきているのか、感じていたにちがいない。ヨハネ福音記者は、「マリアのところに来て、イエスのなさったことを目撃したユダヤ人の多くは、イエスを信じた。しかし、中には、ファリサイ派の人々のもとへ行き、イエスのなさったことを告げる者もいた」(ヨハネ11,45~46)という記事を挿入している。ここで福音記者が、「マリアのところに来て」とわざわざ書いているところから、マリアは、祭司長たちとファリサイ派の人々が、最高法院を召集して話し合い、イエスを殺そうとたくらんだことを、人づてに知っていた可能性がある。彼らは確かにイエスを殺そうと決めたのである(ヨハネ11,47~57参照)。
マリアは、危険を伴うような緊張感が辺りを埋め尽くしていることを感じていた。先生は決起し、もう自分の所に帰って来ないかもしれないと察した。この夕食が最後になるかもしれない。彼女は決心する。マリアは、ナルドの香油を塗ったイエスの足が、今夜同じ香りのする彼女の髪を求めて、彼女の床に入ってくるというフィクション(虚構)を思い描いたにちがいない。彼女は、自分を「イエスの花嫁」、「キリストの花嫁」にしたのだ。
そのとき、弟子の一人で後にイエスを裏切るイスカリオテのユダが、マリアに向かって、「なぜ、この香油を三百デナリオンで売って、貧しい人々に施さなかったのか」(ヨハネ12,5)と言った。イエスはそれをたしなめたが、その言葉はそっけなかった。これに対して、マタイとマルコの福音書の中でイエスは、頭に香油を注ぎかけた女の動機を、「わたしの体に香油を注いで、わたしを葬る準備をしてくれた」(マタイ26,12)、「この人はできるかぎりのことをした。つまり、前もって私の体に香油を注ぎ、埋葬の準備をしてくれた」(マルコ14,8)と語り、あわせて、「なぜ、この人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ」(マタイ26,10、マルコ14,6)ととりなしている。さらに、「よく言っておく。世界中どこでも、この福音が宣べ伝えられる所では、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろう」(マタイ26,13、マルコ14,9)とまで言っている。しかし、ヨハネ福音書のこの場面でのイエスは「この人のするままにさせておきなさい。わたしの葬りの日のために、それを取って置いたのだ」(ヨハネ12,7)と言っただけであった。
ヨハネ福音記者は、「貧しい人々に施さなかったのか」と言ったユダの言葉の後に、「彼がこう言ったのは、貧しい人々のことを心にかけていたからではない。自分が盗人であり、金入れを預かっていて、その中身をごまかしていたからである」(ヨハネ12,6)と解説をしている。福音記者は、ベタニアのマリアを、この「弟子の一人で後にイエスを裏切るイスカリオテのユダ」と並べて書いた。それは、ヨハネ福音記者の眼差しを通して見ると、イエスから手ほどきを受けた直弟子であったにもかかわらず、フィクション(虚構)の世界をつくり、そこに浸りながらイエスを観ていたマリアの姿と行為が、ユダのこれらの状況と重なって見えたからに違いない。彼らは、イエスとともに過ごし、神が人々の中にいるという現実を経験していながら、自分たちが編んだフィクション(虚構)の中で生きていた。そして、この二つの世界の間に矛盾が起こっていることを見ようともしなかった。人が矛盾を解くことができるように、創世記で善悪の知識に神が置いた「敵意」そのものであったイエスは、彼らから完全に無視されたのである(「神学の河口」№14参照)。
イスカリオテのユダとベタニアのマリアの行為は、彼ら自身が作り出したフィクション(虚構)の中から出てくる。これらは、複数の人がともにいることによって共有するようになった偶発的情報(
「神学の河口」№11参照)を「蛇」と呼んで擬人化したエバから始まり(創世記
3,13参照)、進化した姿である(
「神学の河口」14参照)。フィクション(虚構)を創り出し、それを言語によって他者と共有する能力を持った人類は、飛躍的に発展した。しかし同時に、フィクション(虚構)は、アダムを起源とする、自分が持った矛盾の原因を神(他者)の行為に帰し、五感データに残る自分の行為の記憶を正当化する(
「神学の河口」№14参照)という傾きといっしょになって、「人間の仕業」を産み出すことになった。アダムとエバの行為によって決定づけられた「人間の仕業」に至る人の運命は、イエスが罪を贖い、降臨する聖霊と人々のために、すべてを完全に準備したことによって、人を創造の初めに神が言われた神の計画
*へと、確実に舵を取り直した。ヨハネ福音記者は、聖霊とともに生きるキリスト者が、聖霊によってイエスの準備したすべてを使いこなしていくために、これらを迫害の渦中で守りながら、後世に伝えることに挑戦したのである。
*「神は言われた。『我々のかたちに、我々の姿に人を造ろう。そして、海の魚、空の鳥、家畜、地のあらゆるもの、地を這うあらゆるものを治めさせよう』」(創世記1,26)。
つづく
2020年9月 広島にて

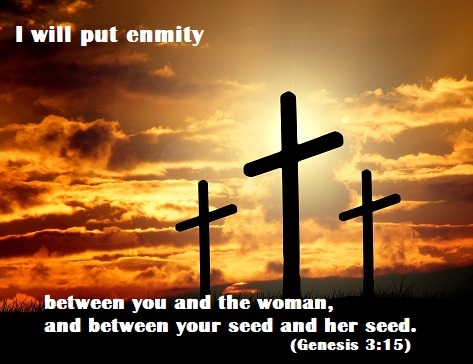
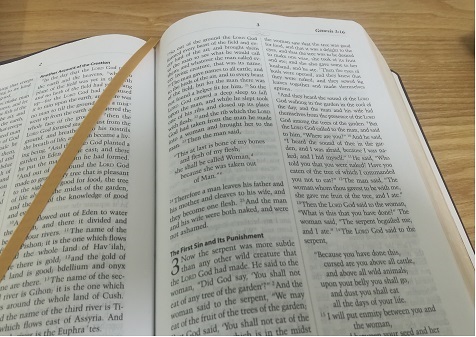
コメント
コメントを投稿