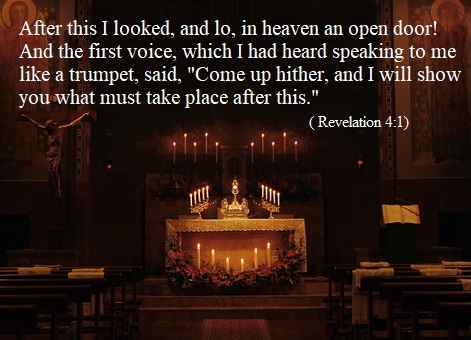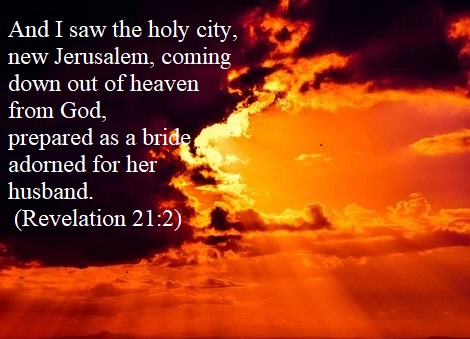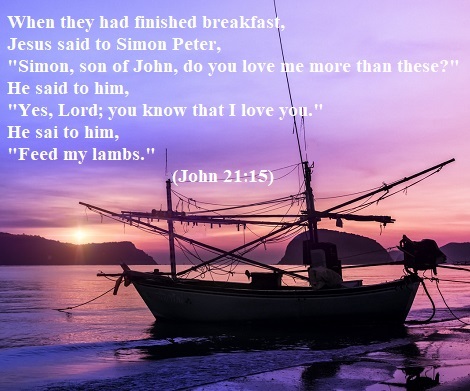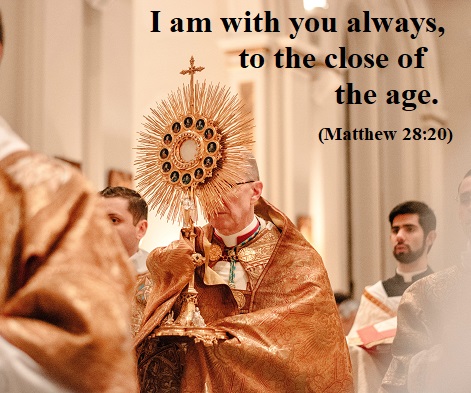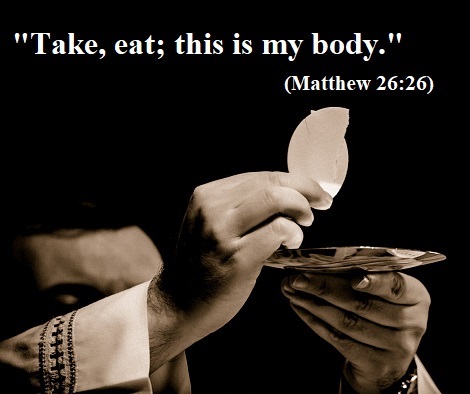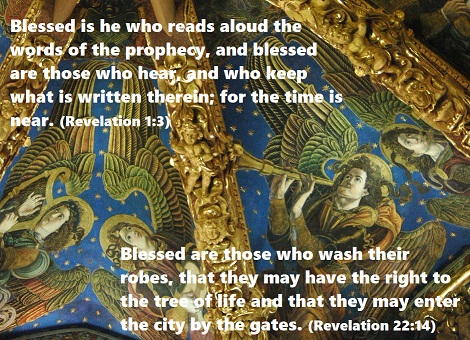
神学の河口21 福音記者ヨハネの挑戦(4) ヨハネの黙示は、「神の計画」を感覚で受け取るための訓練の書である。そのために内容を把握していることは、言葉の持つイメージを感覚に入りやすくさせる。前回、黙示録を3つの部分に分けて、第一部、第二部について扱った。そこで、続けて第三部から、その要点を考察し、この訓練が目指すところもはっきりさせておきたい。 「また、天に大きなしるしが現れた。一人の女が太陽を身にまとい、月を足の下にし、頭には十二の星の冠をかぶっていた」(黙示録12,1)。前回考察したように、この「天」は、聖霊によってもたらされた「天」である。「一人の女が太陽を身にまとい」の「太陽」は、「顔は強く照り輝く太陽のようであった」(黙示録1,16)と書かれた方を指し、彼女はこの方の栄光を身にまとっているのである。この文は、天使がマリアに告げた「聖霊があなたに降り、いと高き方の力があなたを覆う」(ルカ1,35)という言葉と符合する。そして、イエスが、ご自分の母に、「女よ」と語りかけたことを思い出すと(ヨハネ2,4、19,26参照)、この「一人の女」から、「イエスの母マリア」(使徒言行録1,14参照)のイメージが浮かんでくる。 この女性は、この世の夜を照らす「月」を足の下にしている。「月」が地上の事柄を指すと捉えれば、「月を足の下にし」という言葉は、「天」に現れた彼女が、未だ地上の事柄に関わっていることを示唆している。頭にかぶっている冠の「十二の星」の「星」は、天使を指している(黙示録1,20参照)。これは、「都には高い大きな城壁と十二の門があり、それらの門には十二人の天使がいて、名が刻みつけてあった。イスラエルの子らの十二部族の名であった」(黙示録21,12)と書かれている「十二の門の天使」である。この天使たちは、悪霊を麦と毒麦に分けて自由な意思を救っているのである( 「神学の河口」№16 参照)。そこで、この「十二の星」の冠は、神の救いの業が継続されていることの象徴である。実際にイエスの母マリアは、神の独り子と親子の関係になることを承諾し(ルカ1,26~38参照)、救い主の母となった。さらに十字架上のイエスの指示に従って、「愛する弟子」と親子の関係を結ぶことを承諾した(ヨハネ19,26~27参照)。これによって「愛する弟子」、すなわち使徒は、救い主の母としての全権を継