神学の河口19
福音記者ヨハネの挑戦(2)
ヨハネ福音記者は、迫害の中で、「私の教会」(マタイ16,18参照)の重要機密であるキリストの司祭職の特徴を、「花嫁」と「イエスの愛しておられた弟子」の言葉の中に隠した。これらの言葉は、女性をイメージさせることから、これを隠すために好都合であった。司祭職の主たる職務が、イエスが制定したキリストの聖体が生まれるために、聖霊の伴侶となる役割を受け取ることであるから、そう遠くない表現だったと言える。ヨハネ福音記者は、イエスがご自分を花婿にたとえ、弟子たちをその婚宴に招かれた友人、母、兄弟姉妹として見ていたことに注目した。そこで、イエスが一度も使わなかった「花嫁」という言葉を、自分の書いた福音書だけに載せることで、イエスが命をかけて準備した、聖霊と「私の教会」にとって、なくてはならない司祭職に、キリスト者の注意を向けようとした。
ヨハネ福音記者は、イエスの初めの弟子たちが、洗礼者ヨハネの弟子であったことを伝えている(ヨハネ1,35~37参照)。彼らは、洗礼者ヨハネに促されて、自発的にイエスについて行ったのである。やがて自分のもとに残っている弟子たちから、みんながイエスのところに行くようになったことを聞いた洗礼者ヨハネは、彼らに言った。「人は、天から与えられなければ、何も受けることはできない。『私はメシアではなく、あの方の前に遣わされた者だ』と私が言ったことを、まさにあなたがたが証ししてくれる。花嫁を迎えるのは花婿だ。花婿の介添え人は立って耳を傾け、花婿の声を聞いて大いに喜ぶ。だから、私は喜びで満たされている。あの方は必ず栄え、私は衰える」(ヨハネ3,27~30)。ここで洗礼者ヨハネが「花嫁」と言ったのは、イエスの弟子になった者たちを指していたのである。
ヨハネ福音書では、「花嫁」が1度、「花婿」が4度出てくる。ヨハネの黙示録には、反対に「花婿」が1度「花嫁」とともに、また「花嫁」が単独で4度出てくる。この数の符合は、ヨハネ福音書と黙示録の関係に注目させる。黙示録に「花嫁」とともに1度出てくる「花婿」が、次のように、イエスの受難と死をイメージしていると捉えると、そこでともに並べられた「花嫁」は、散らされ、殉教した弟子たちを想像させる。「灯の明かりも、もはやお前のうちには輝かない。花婿や花嫁の声も、もはやお前のうちには聞かれない。なぜなら、お前の商人たちが地上の高官となり、また、お前の魔術によって、すべての国の民が惑わされ、預言者と聖なる者たちの血、地上で屠られたすべての者の血が、この都で流されたからである」(黙示録18,23~24)と書いてあるからである。
ヨハネ福音記者は、エルサレムを嘆き(マタイ23,37~39、ルカ13,34~35、19,41~44参照)、滅亡の予告をするイエスの言葉を近くで聞いた(マタイ24,1~8、マルコ13,1~8、ルカ21,5~24参照)。この時、福音記者は、イエスがキリスト者のために、エルサレムに替わる新しい都の計画を持っていると予感したに違いない。エルサレムが崩壊するならば、キリスト者は、その拠点をどこに置けばいいのだろうか。実際イエスの予告通りにエルサレムが滅んだ後、この予感を確信にした彼は、自分の福音書にイエスとピラトのやりとりをくわしく書き残した(ヨハネ18,33~38、19,8~11参照)。
ピラトは、イエスがユダヤ人の王であるかどうかに固執していた。そこでイエスは、彼が、「お前がユダヤ人の王なのか」と尋問したとき、「それは、あなたが言っていることです」と答えている(マタイ27,11、マルコ15,2、ルカ23,3参照)。マタイ福音書は、「ピラトが裁判の席に着いているときに、妻から、『あの正しい人に関係しないでください。その人のことで、わたしは昨夜、夢で随分苦しめられました。』という伝言があった」(マタイ27,19)ことを記載した。ピラトはこのような不安材料に、イエスに対する畏れのような何かをいよいよ大きくし、胸騒ぎを感じていたにちがいない。
イエスと出会ったピラトは、この人物のまなざしに、いつか広まらずにはいないイエスの「王道」を、イエスの狙いを、感じ取ったかもしれない。イエスがユダヤ人の王であるかどうかにこだわる彼は、「この男」をユダヤ人の王として終わらせることで、彼の胸騒ぎを鎮め、それを振り払おうとしているように見える。そして「罪状書き」の場面(ヨハネ19,19~22参照)では、彼自身が、「わたしが書いたものは、書いたままにしておけ」と言った。つまり公に「ナザレのイエス、ユダヤ人の王」という罪状書きをかかげることで、自分と「この男」とのつながりを完全に終わらせ、安心したかったのではないだろうか。マルコ福音書は、イエスの死後、「ピラトは、イエスがもう死んでしまったのかといぶかり、百人隊長を呼び寄せて、もうすでに死んだのかと尋ねた」(マルコ15,44)と書いている。イエスは彼の最期の日、確かにローマを、新しいエルサレムのために選んでいたのだ。
ヨハネの黙示録は、この後キリスト者のものとなる新しい都で、まるで新しいエルサレムがキリスト者の前に現れるような出来事を、預言者の目で見たものである。そこでヨハネは、「天使はまた、私にこう言った。『これらの言葉は、信頼でき、また真実である。預言者たちに霊感を授ける神、主が、その天使を送って、すぐに起こるべきことを、ご自分の僕たちに示されたのである』」(黙示録22,6)、「これらのことを聞き、また見た者は、私ヨハネである」(黙示録22,8)と書いた。聖霊降臨を経験し、聖霊が、イエスが準備したすべてを再び生きるものとするのを見たヨハネは、イエスがキリスト者のために、都を準備していないはずはないと確信していた。
「すると、玉座におられる方が言われた。『見よ、私は万物を新しくする。』また言われた。『書き記せ。これらの言葉は信頼でき、また真実である。』また、私に言われた。『事は成った。私はアルファであり、オメガである。初めであり、終わりである。渇いている者には、命の水の泉から価なしに飲ませよう。勝利を得る者は、これらのものを受け継ぐ。私は彼の神となり、彼は私の子となる』」(黙示録21,5~7)。
神は、ダビデに、その子ソロモンについて、「私は彼の父となり、彼は私の子となる」(サムエル記下7,14、歴代誌上22,10、28,6参照)と言った。しかし、この言葉は、ソロモンの背きによって実現しなかった。ソロモンは、永遠の花婿と花嫁の関係を描いた「雅歌」の世界を楽しんだ。「ソロモンが年老いたとき、女たちは彼の心を、他の神々へと向けさせた」(列王記上11,4)。彼は、「私は彼の父となり、彼は私の子となる」と言った関係を与えようとした神の現実ではなく、自分のフィクション(虚構)を追い求めたのである(列王記上11,1~10参照)。イエスは、人々に天の父の名を知らせ、神と人の間に御父と御子の関係を与えた。
黙示録に「都の城壁には十二の土台があり、そこには小羊の十二使徒の十二の名が刻みつけてあった」(黙示録21,14)と書いてあるところから、「城壁」は、祭壇を囲む司祭たちである。同様に「私に語りかけた天使は、都と門と城壁を測るために、金の物差しを持っていた。この都は四角形で、長さと幅が同じであった。天使が物差しで都を測ると、一万二千スタディオンあった。長さも幅も高さも同じである」(黙示録21,15~16)と書かれた「都」は、祭壇である。「これは人間の尺度であって、天使が用いたのもこれである」(黙示録21,17)というフレーズからも、城壁と都が具体的な事柄を指していることが分かる。ミサの中で司祭たちと祭壇は、夫のために装った花嫁のように支度を整えて、まるで神のもとを出て、天から降って来るように、人々の眼前に現れる。「都の門」は、白くて丸い真珠にたとえられたキリストの聖体である(黙示録21,21参照)。「都には高い大きな城壁と十二の門があり、それらの門には十二人の天使がいて、名が刻みつけてあった。イスラエルの子らの十二部族の名であった」(黙示録21,12)とあるように、この門にいる天使は、キリストの聖体によって、悪霊を分けて自由な意思を救っているのである(「神学の河口」№14参照)。ヨハネは、聖体が祭壇の上に顕示されている未来を見ていた。
「霊と花嫁が共に言う。『来りませ。』これを聞く者も言うがよい。『来りませ。』」(黙示録22,17)。「霊」と「花嫁」、そして「これを聞く者」は、聖霊と司祭たちと信徒たちである。キリストの聖体はすでに来た。聖体は、神の国の到来と世の終わりを示す門である(「神学の河口」№14参照)。ヨハネ福音記者は、聖体が生まれるために、聖霊の伴侶となる司祭職を、「花嫁」の言葉に隠した。
共観福音書は、イエスの最後の食事の場面を「除酵祭の第一日に」、「除酵祭の日が来た」(マタイ26,17、マルコ14,12、ルカ22,7参照)と書いて、過ぎ越しの食事の準備の場面から始めている。これに対して、ヨハネ福音書は、イエスの最後の食事の場面を、「過越祭の前に」(ヨハネ13,1)という言葉で始めている。ヨハネ福音記者が、わざわざ「前に」と書いたのは、この言葉にキリスト者の注意を向けて、イエスが聖体を制定する「前に」、弟子の足を洗う場面があったことを伝えるためであった。神が、エジプトを脱出した民に、ご自分が選んだ祭司を清めるよう命じたように、イエスが、聖体を制定する「前に」、ご自分が選んだ使徒たちの足を洗って清め、使徒たちを新しい司祭として聖別したことを、福音記者は伝えた。そこで、この場面でのイエスとペトロとのやりとりの中に、神がモーセに命じた言葉と符合する言葉が出てくるのである(出エジプト30,17~21、40,30~31/ヨハネ13,6~10参照)。
イエスは、「私があなたがたにしたとおりに、あなたがたもするようにと、模範を示したのだ。よくよく言っておく。僕は主人にまさるものではなく、遣わされた者は遣わした者にまさるものではない。このことが分かり、そのとおりに実行するなら、幸いである」(ヨハネ13,15~17)と言って、神ご自身の手で聖別した司祭職を継承していくように命じた。この「幸い」は、イエスが「それで、主であり、師である私があなたがたの足を洗ったのだから、あなたがたも互いに足を洗い合うべきである」(ヨハネ13,14)と言ったように、使徒たちがイエスの模範のとおりにこれを実行し、神の手から受けた司祭職の聖別を次の世代に伝えていく「幸い」である。こうしてイエスが司祭職を聖別した場面を詳しく書いたヨハネ福音記者は、自分の福音書に聖体制定の場面を載せなかった。彼は、重大なこの二つの事柄が直接つながり、新しい司祭職が、迫害者の攻撃の的にされることを恐れたのである。
イエスの最後の夕食で、イエスの胸元に寄りかかっていた「イエスの愛しておられた弟子」の姿は、聖霊の伴侶となるために神によって聖別された司祭の姿である(ヨハネ13,23~26参照)。福音記者は、この「イエスの愛しておられた弟子」と言う言葉を、復活したイエスとペトロとの会話の場面でも再び繰り返し、その重要性を強調した。「ペトロが振り向くと、イエスの愛しておられた弟子が付いて来るのを見た。この弟子は、あの夕食のとき、イエスの胸元に寄りかかったまま、『主よ、あなたを裏切るのは誰ですか』と言った人である」(ヨハネ21,20)。
さらに福音記者は、その次の場面でもイエスの言葉を2度繰り返して強調した。「ペトロは彼を見て、『主よ、この人はどうなるのでしょうか』と言った。イエスは言われた。『私の来るときまで彼が生きていることを、私が望んだとしても、あなたに何の関係があるか。あなたは、私に従いなさい。』それで、この弟子は死なないという噂がきょうだいたちの間に広まった。しかし、イエスは、彼は死なないと言われたのではない。ただ、『私の来るときまで、彼が生きていることを、私が望んだとしても、あなたに何の関係があるか』と言われたのである」(ヨハネ21,21~23)。
ここには、この時すでに天の父とイエスご自身の選びによって(マタイ16,17~18参照)使徒たちの頭として置かれていたペトロには関係のない神の計画が隠されていた。ペトロが家族持ちであったことから、イエスは彼に、「私の来るときまで彼が生きていることを、私が望んだとしても、あなたに何の関係があるか。あなたは、私に従いなさい」と言ったのである。そして福音記者は、「これらのことについて証しをし、それを書いたのは、この弟子である。私たちは、彼の証しが真実であることを知っている」(ヨハネ21,24)と書いた。彼がこれほどまでにこのやり取りを重要視したのは、「私の来るときまで彼が生きていることを、私が望んだとしても」と言う言葉が、「イエスの愛しておられた弟子」の召命に関わることだったからである。それは、イエスが、「イエスの愛しておられた弟子」に示された「神の独身性」(「神学の河口」№9参照)を受け取る司祭職が、イエスの再臨まで続いていくと示唆していたからである。
創世記の記述から、司祭職は男性の上に定められていた。「イエスの愛しておられた弟子」とは、司祭職が、ただ男性であることだけではなく、「神の独身性」を持つ男性に任されるようになるということである。それは、「神の独身性」を持つ聖霊とじかにつながる司祭に相応しいことであった。「神の独身性」とは、めとることも嫁ぐこともない神の命である神の意思の特性であり、三位一体の神が、それぞれ自ら「わたしはある」という方として、神の知識で一体になりながらも、それぞれの意思が独立し、互いに意思を抱え込む依存の関係にないことからきている(「神学の河口」№9参照)。
神が、初めから人を男と女とにお造りになったのは、他の生き物のように、「産めよ、増えよ」(創世記1,22)と言った神の言葉を実現するためだけではない。この言葉と同時に生き物に与えられた生殖能力は、人の創造の完成を支えるものであって、目的ではない。とはいえ、神に似せて、神にかたどられて創られた人は、朽ちる肉体の中に宿る命が、神の創造の全計画を支える貴重なものであることを、“知識”によって受け取るのである。人は、生殖能力が神の計画の協力者となるためにあると“知る”ことができる。それは、創世記3章を考察することで明らかになる。
創世記3章は、人が、神が禁じた善悪の知識の木の実を食べた経緯(創世記3,1~13)、その結果生じた問題と、問題への神の対処(「神学の河口」№14参照)を含む神の計画(創世記3,14~19)、そして最後に、エデンの園から追放される直接の原因になった人の行為(創世記3,20)を記している(「神学の河口」№12参照)。ここに、神が女に告げた「あなたは夫を求め、夫はあなたを治める」(創世記3,16)というフレーズと、男に告げた「土から取られたあなたは土に帰るまで額に汗して糧を得る」(創世記3,19)というフレーズがある(「神学の河口」№6参照)。この二つは神が初めから持っていた計画であった。神が女に告げたフレーズは、女性と男性が、遺伝子によって互いの経験の記憶を分かち合いながらも、生殖機能の違いから、まったく異なる召命に向かって創造されていることを伝えている。
女性が任された人の卵子は、女性が胎児であったときに、その母の胎内で作り上げられ、女性が出生後、新たに作られることはない。成長した女性の体内で、卵子は、28日から1か月ほどの周期で成熟し、精子を求めて卵管に出てくる。女性はこの卵子の影響を強く受けてこの期間に発情する。排卵は、女性の意志とは無関係に起こるために、女性はその構造上、排卵と発情することをコントロールできない。そして、精子と出会わず受精卵にならなかった卵子は、出血を伴ってはがれる子宮の一部とともに、体外に排出される。神は、神の計画によって、初めから女性を、み言葉が人を創造する業を成し遂げるための助け手として創った。土をこねる神のみ手の代わりとなって、胎内に自由な意思を宿す可能性を常に保持している女性は、本性的に「神の独身性」を持たない方向に置かれている。これが、女性の召命である。たとえ年老いて閉経したとしても、サラも、エリザベトも妊娠したのである。神にはできないことがない。
しかし、イエスの時代には、たとえ妊娠する可能性を持っていても、他者の意思を一度も抱えず「神の独身性」を保っていたイエスに倣い、また、イエスが両親に仕えて暮らしたように(ルカ2,51~52参照)、イエスの「私の教会」に仕えて暮らしたいと望む女性たちがすでにいた。また、男性の中にも同じ望みを抱く者がいたにちがいない。彼らは「イエスのみ名」を受け取り、イエスの役割を生きる者である(「神学の河口」№8参照)。したがって、「イエスのみ名」を受け取る者は、「神の独身性」を持っている必要がある。
一方、男性が成長すると、体内でつくり出されるようになる精子は、古くなると体内に吸収され、新しくつくられた精子と交換される。精子は、男性の体内に常に一定量が保たれている。男性は、この仕組みのために、通常精子を体外に排出する必要はない。神は男性に、自分の意志によって発情をコントロールできる体の構造を与え、自らを治め、女性の発情も治めるように計らった。神は、男性を、「神の独身性」を持って聖霊の働きをじかに受けることができるように創造し、男性の上に、聖霊の伴侶としての祭司職を与えるよう計画したのである。この計画は、すべての生き物に「産めよ。増えよ。」と言って生殖機能を与えた神の言葉と矛盾を起こすことはない。神は人々を祝福し、「産めよ、増えよ、地に満ちて、」(創世記1,28参照)と言ったように、「地に満ちて」という上限を定めたからである。これを治めるのは男性である。これが、御父の意志であり、「あなたは夫を求め、夫はあなたを治める」と言ったみ言葉の真意である。神はこのために、「人」から女を取ったとき、そのあとを「肉で閉ざした」(創世記2,21参照)。
やがて神は、アブラハムに、「私とあなたがた、およびあなたに続く子孫との間で守るべき契約はこれである。すなわち、あなたがたのうちの男子は皆、割礼を受けなければならない」(創世記17,10)と命じて、「神が閉ざした肉」を聖別した。これによって神は、アブラハムの一族の男性が、未来に祭司職を受け取ること、さらに、もっと未来に新しい司祭職を男性が受け取ることを公に示したのである。
司祭職は、創造の初めから男性が受け取る召命であった。そこで、神の計画のすべてを担って地上に来たイエスは、このように、男性の体の構造から、男性に貞潔を求めた。しかしこの時代、まだ誰もこれらの知識がなかったので、弟子たちは、イエスの言葉に反発して言った。「人が妻と別れてはならない理由がそのようなものなら、結婚しないほうがましです」(マタイ19,10)。そこでイエスは言った。「誰もがこの言葉を受け入れるのではなく、恵まれた者だけである。独身者に生まれついた者もいれば、人から独身者にされた者もあり、天の国のために自ら進んで独身者となった者もいる。これを受け入れることのできる人は受け入れなさい」(マタイ19,11~12)。イエスは、弟子たちが現在の状況のままでも、自発的に「神の独身性」に向けて生きることを勧めた。それは、将来彼らが司祭となり、「神の独身性」を持つ聖霊の働きを受けて、キリストの聖体が生まれるようになるからである。
やがてその必要から、司祭職は、「神の独身性」に向けて歩んでいく。イエスが示した「天の国のために自ら進んで独身者となること」は、法律上未婚であることだけではなく、聖霊に向かう「神の独身性」を求めている。男性は、「あなたは夫を求め、夫はあなたを治める」(創世記3,16)という神の言葉の真意をよく知り、この言葉の重要性を教育され、十分に訓練を受ければ、人の命の“始め”になる自身の生きている精子の責任を、治める者になるにちがいない。そこでイエスは、「弟子は師を超えるものではない。しかし、誰でも、十分に訓練を受ければ、その師のようになれる」(ルカ6,40)と言ったのである。
この後、ペトロはイエスに言った。「このとおり、私たちは何もかも捨てて、あなたに従って参りました。では、私たちは何をいただけるのでしょうか」(マタイ19,27)。イエスは一同に言われた。「よく言っておく。新しい世界になり、人の子が栄光の座に着くとき、私に従って来たあなたがたも、十二の座に着いて、イスラエルの十二部族を裁くことになる。また、私の名のために、家、兄弟、姉妹、父、母、子、畑を捨てた者は皆、その百倍もの報いを受け、永遠の命を受け継ぐ」(マタイ19,28~29)。
この後イエスは、「しかし、先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になる」(マタイ19,30)と付け加えた。この言葉の直後には「ぶどう園の労働者のたとえ」が置かれている(マタイ20,1~16参照)。このたとえも、「このように、後にいる者が先になり、先にいる者が後になる」というフレーズで終わる。このみ言葉の真意は、次にイエスが最後の受難の予告をした後(マタイ20,17~19)、ゼベダイの息子たちの母が、息子たちと一緒にイエスのところに来て、願い事をした出来事(マタイ20,20~23参照)を読むと理解することができる。母親が出てきたことから、彼らはまだ両親のもとにいて、独身者であったにちがいない。イエスと同じ独身者であったからこそ、イエスの語った「恵まれた者」として、イエスのみ国で、彼の右と左に座ることを望んだのである。結局イエスは、彼らの願いを否定しなかった。そこで「ほかの十人の者はこれを聞いて、この二人の兄弟のことで腹を立てた」(マタイ20,24)とある。
イエスは一同を呼び寄せ、「あなたがたの中で偉くなりたい者は、皆に仕える者となり、あなたがたの中で頭になりたい者は、皆の僕になりなさい」と諭した(マタイ20,25~28参照)。しかし他の10人が腹を立てたのは、彼らが家族持ちであったからにちがいない。家族持ちが、イエスの名のために、家、兄弟、姉妹、父、母、子、畑を捨ててイエスに従い、天の国のために自ら進んで独身者となることと、初めから独身者であった者がそうすることとが、同じ苦労ではありえない。実際、他の10人が家族持ちであったならば、「最後に来たこの連中は、一時間しか働かなかったのに、丸一日、暑い中を辛抱して働いた私たちと同じ扱いをなさるとは」(マタイ20,12)と言ったぶどう園の労働者と同じ気持ちになったであろう。しかしそれでもイエスは、「友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と一デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後の者にも、あなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分の物を自分のしたいようにしては、いけないのか。それとも、私の気前のよさを妬むのか」(マタイ20,13~15)と答えたにちがいない。イエスは、そこで、「このように、後にいる者が先になり、先にいる者が後になる」と付け加えたのである。
キリストは、御父の意志を担って地上に来た。これとは異なり司祭は、キリストの聖体が生まれるために聖霊の働きをじかに受けたとき、み言葉によって表された御父の意志を抱え込むのである。司祭は、イエスを身ごもったマリアとよく似た状態になる。祭壇の上で、パンと葡萄酒がキリストの御体と御血になるように祈り、このキリストの体と血の杯を上げる時、司祭は、まさにキリストの聖体を支える十字架になる。キリストの聖体は、司祭の手に支えられ、十字架上ですべての人を自分のもとに引き寄せるキリストの姿を現すのである(ヨハネ12,32参照)。「わたしの記念としてこのように行いなさい」(ルカ22,19)というイエスの命令の真意が、ここに実現する。このためにイエスは、十字架上で、「愛する弟子」に母を与えた(ヨハネ19,27参照)。十字架上のイエスの言葉によって、イエスの母と弟子の間に結ばれた母と子の絆は、キリストの聖体を上げる司祭を勇気付け、キリストの十字架となってキリストの聖体にくぎ付けにされた司祭を、同時に、その下でイエスの母と共にいる「イエスの愛しておられた弟子」にする。
つづく
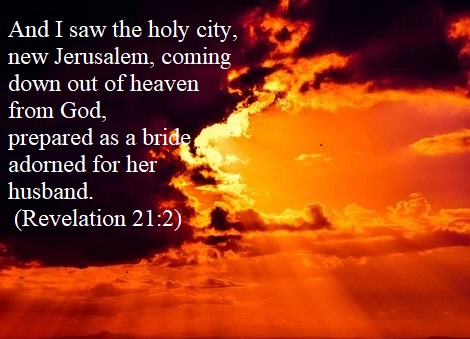
コメント
コメントを投稿