神学の河口16
キリストの聖体(2)
神は、初めて殺人の罪を犯したカインと、それによって初めて死んだ人となったアベルについて、またこの人々と同じ運命を辿ることになる多くの人々の必要のために、神の計画に第2の救いの計画を加えた(「神学の河口」№15参照)。カインは、神にとって、「産めよ、増えよ、地に満ちて、これを従わせよ。海の魚、空の鳥、地を這うあらゆる生き物を治めよ」(創世記1,28)という言葉を実現する初子であった。「産めよ、増えよ」と言った神の意に反して、神が初めて罪と呼ぶことになった殺人を犯した彼は、神が置いた「敵意」(創世記3,15参照)によって、「私の過ちは大きく、背負いきれません」と言うことができた。神は、この言葉によって彼を赦した。そして、カインの犯した罪と、カイン自身が宣言した彼の負うべき罰を、次のように神ご自身が文字通りに引き受けた(「神学の河口」№14参照)。
カインは、「あなたは今日、私をこの土地から追放されたので、あなたの前から身を隠し、私は地上をさまよい、さすらう者となり、私を見つける者は誰であれ、私を殺すでしょう」(創世記4,14)と言った。この言葉を、神の独り子であるイエスが、天の父のもとから降り、彼自身が「狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが、人の子には枕する所もない」(マタイ8,20)と言った者となり、ついに見つけられて十字架刑によって殺されることで引き受けたのである。そして、神が自由に死に(ヨハネ10,17~18参照)、黄泉に降ることによって、それまでに死んだ人の自由な意思を救った。そこで、十字架の死の後には、空の墓のエピソードが続く。
祭司長たちとファリサイ派の人々が、墓からイエスの遺体が盗まれるかもしれないと心配していたように(マタイ27,62~66参照)、弟子たちもまた、主が復活することよりも、主の遺体が墓から取り去られることを心配していたことが、わずかな福音書の記述から察せられる(マタイ27,61、ヨハネ20,1~2参照)。そこで、ヨハネ福音書記者も、空の墓の場面の終わりに、「イエスが死者の中から必ず復活されることを記した聖書の言葉を、二人はまだ理解していなかったのである」(ヨハネ20,9)と書いた。しかし福音書記者は、その前に、「先に墓に着いたもう一人の弟子も中に入って来て、見て、信じた」(ヨハネ20,8)と書いている。これを書いた福音書記者の意図はどこにあったのであろうか。
イエスから選ばれて、ペトロとヤコブとともにイエスの特別な場面に何度も居合わせていたヨハネは(マタイ17,1、26,37、マルコ5,37、9,2、14,33、ルカ8,51、9,28参照)、墓の中に入って、イエスの頭を包んでいた覆いが、亜麻布と同じ所には置いてなく、離れた所に丸めてあったのを見た(ヨハネ20,7参照)。そして、何かに気づいた。それはイエスの最後の食事の場面であったに違いない。すなわちそれは、「これは、あなたがたのために与えられる私の体である」(ルカ22,19)というイエスの言葉であった。そのときわからなかったからこそ、彼の記憶に強烈に残った言葉であった。彼は、まさに今、この言葉が実現しているのを見た。空の墓と残されていた覆いや亜麻布は、その証であった。彼はここで、これを「見て、信じた」のである。そこで、ヨハネ福音書記者は、三共観福音書がすでに書いていた聖体制定の場面を、かえって描かなかった。むしろイエスが、パンを増やした後、「命のパン」について群衆に語った場面を、力をこめて書いた。空の墓の中に立ったヨハネの内奥で、イエスの聖体制定の言葉と、命のパンについて群衆に語った言葉が、一つにつながったのである。
神の計画は、天地のすべてものが、神の「あれ」という言葉によって生まれ、存在することに始まった(創世記1,1~31参照)。すべての生き物の死は、神の言葉「あれ」がその使命を成し遂げて、神が創造したその生き物の体と、その生き物に相応の感覚の記憶から抜け出し、神のもとに帰還し、神の認識となって終わる(「神学の河口」№4参照)。生き物の「あれ」は、死を通って神のもとに帰る。神の言葉は、神の望むことを成し遂げ、神が与えた使命を必ず果たす(イザヤ55,10~11参照)。しかし、自由な意思を持つ人の死は、他の生き物と同じではない。アベルのように突然殺されて、自分の死の認識を持たずに死に、神の言葉「あれ」とともに、自由な意思がいきなり体の外へ放り出されるケースが起こる。神が「何ということをしたのか。あなたの弟の血が土の中から私に向かって叫んでいる」(創世記4,10)とカインに言ったように、アベルの自由な意思は、神に向かって叫び声を上げたのである。
「これは、あなたがたのために与えられる私の体である」(ルカ22,19)と言ったイエスは、ご自分の死によって、イエスが現れるまで、この世に残り、待っていたこれらの自由な意思に向かい、これらをすべて引き寄せ、主の「羊の囲い」(ヨハネ10,1~5参照)の中に連れて行った。そこでイエスは、復活し、昇天するご自分の未来においても、聖霊がイエスの霊としてこの救いを継続するために、「渡される夜」に聖体を制定したのである。地上に神がキリストの聖体として現存し、キリスト者の協力によって絶えず死に、神の救いの業を続けることは、すべての人の自由な意思の救いのために、必要不可欠であった。キリストの聖体は、キリスト者が食べるとき、その人の中で死に、そこから神の現存が抜け出て、これらの自由な意思を、主の「羊の囲い」に連れて行く機会を得る。こうしてイエスは、この第2の神の救いの計画の継続を、イエスの名によって遣わされた聖霊とキリスト者に委ねた。
聖霊の意思は、地上に残るイエスの言葉である神の知識と結ばれて、イエスの霊を出現させる。このように、霊とは、意思と知識の結合である。悪霊も霊であって、サタン(悪魔)ではない。人がサタン(悪魔)化した状態(「神学の河口」№12参照)のままで死んで、この人の自由な意思が、「蛇」の情報(偶発的情報)と離れる機会を失ったとき悪霊になると考える。
創世記で、女と「蛇」の対話の中で言われた、「いや、決して死ぬことはない」(創世記3,4)という「蛇」の言葉は、女の五感データに発生した「蛇」の情報(偶発的情報)であった(「神学の河口」№14参照)。この言葉は、その後、女が善悪の知識の木の実を食べても死ななかったことから実証され、善悪の知識の中で強固な認識となって、初めに創造された女を通してすべての人のものになった(「神学の河口」№14参照)。サタン(悪魔)化した人がその状態のまま死に、この人の自由な意思が、「いや、決して死ぬことはない」という認識を持っている善悪の知識に執着している場合、肉体とともに善悪の知識が死んでも、強固に残るこの認識が、「蛇」の情報(偶発的情報)として自由な意思に貼り付き、死んだこの人を悪霊にすることがある。
この状態に陥った自由な意思は、死によって自身の体とともに善悪の知識と五感データの記憶を失っても、「いや、決して死ぬことはない」という「蛇」の情報(偶発的情報)とともにこの地上に留まり続ける。この自由な意思には、主の「羊の囲い」に入る機会はない。そこで生きている人にとり付き、ともに死んで、死の認識を得ようとする(マルコ5,3~5、ルカ8,29参照)。しかし、生きている人には、自由な意思があるので、とり付いても死ぬことはできない。とり付かれたこの人も悪霊もともに苦しみ、悪霊となった自由な意思は、この人から追い出されれば、再び「蛇」の情報(偶発的情報)とともにこの世を這いずり回る。そして、この情報の死、すなわち第二の死(黙示録2,11、20,6、20,14、21,8参照)と言われている死の前味を味わうのである。しかも、神が吹き入れた永遠の命そのものである自由な意思が死を望む、という矛盾を抱え続けながら。この自由な意思にとって、矛盾を解くために神が人の善悪の知識に置いた「敵意」は、善悪の知識の死とともに、すでにない(「神学の河口」№14参照)。
紫の布や上質の亜麻布を着て、毎日、派手な生活を楽しんでいた金持ちと、彼の門前に横たわる出来物だらけの貧しい人ラザロのたとえ話は、これらのことをよく表わしている(ルカ16,19~31参照)。二人は死んで、ラザロは天使たちによってアブラハムの懐(主の「羊の囲い」)に連れて行かれ、金持ちは、黄泉でさいなまれていた。アブラハムは、その理由を、「子よ、思い出すがよい。お前は生きている間に良いものを受け、ラザロのほうは悪いものを受けた。今は、ここで彼は慰められ、お前はもだえ苦しむのだ」と説明した。しかし、自分も死んでいるのに、「父アブラハムよ、もし、死者の中から誰かが兄弟のところに行ってやれば、悔い改めるでしょう」と言っている金持ちの自由な意思は、自分の死をまだ認識していない。「いや、けして死ぬことはない」という「蛇」の情報(偶発的情報)が貼り付いているのである。このように地上の生活にあまりにも執着していたために、死んでも自分の死を認識にできないまま、知識や記憶、肉体を失った後も、この世に留まって苦しむ自由な意思もいる。
この状態から人の自由な意思を救うことができるのは、神の現存だけである。弟子たちがイエスから与えられた権能によって、人は他者にとり付いた悪霊を追い払うことはできる。しかし、悪霊に死を与えられるのは神だけである(マタイ8,28~32、マルコ5,1~13、ルカ8,26~33参照)。そこで悪霊となった自由な意思は、イエスに出会うまで、「いや、決して死ぬことはない」という「蛇」の情報(偶発的情報)から解放されることはなかった。
イエスのたとえの中で、アブラハムが、「私たちとお前たちの間には大きな淵が設けられ、ここからお前たちの方へ渡ろうとしてもできないし、そこから私たちの方に越えて来ることもできない」(ルカ16,26)と言った「大きな淵」とは、ともに悪霊となって、とり付いている自由な意思を失い、情報としての存在意義が皆無となった「蛇」の情報(偶発的情報)の、いわば墓場である。そこで、「悪霊どもは、自分たちに底なしの淵に行けとお命じにならないようにと、イエスに願った」(ルカ8,31)とある。しかし「蛇」の情報(偶発的情報)は、「世の終わり」まで、この「淵」に置かれることはなかった。
福音書の別の箇所で、悪霊たちが、「神の子、構わないでくれ。まだ、その時ではないのにここに来て、我々を苦しめるのか」(マタイ8,29)と叫んだとある。ここで悪霊たちが言った「その時」が、「世の終わり」である。「世の終わり」とは、聖霊降臨によって「私の教会」(マタイ16,18参照)が創立された後、イエスの最後の食事がミサとして再現され、キリストの聖体が現れる時である(「神学の河口」№15参照)。そこで、このときイエスは、悪霊が、豚の中に入ることを許し、悪霊となった自由な意思に再び死ぬ機会を与えたのである(マタイ8,30~32、マルコ5,11~13、ルカ8,32~33参照)。悪霊の自由な意思は、2度目の死の体験によって、「いや、けして死ぬことはない」という「蛇」の情報(偶発的情報)から、やっと解放されたのである。この神の救いは、ミサによって継続される。
イエスは、悪霊となった自由な意思を解放するこの神の救いがミサの中で継続することを、毒麦のたとえで語った(マタイ13,24~30参照)。ここで、「刈り入れまで両方とも育つままにしておきなさい。刈り入れの時、『まず毒麦を集め、焼くために束にし、麦のほうは集めて倉に納めなさい』と刈り取る者に言いつけよう。』」(マタイ13,30)と言ったイエスは、自由な意思を麦に、「蛇」の情報(偶発的情報)を毒麦にたとえたのである。悪霊としてともにいた、「いや、決して死ぬことはない」という「蛇」の情報(偶発的情報)と自由な意思は、「刈り取る者」によって分けられる。死んだ人の自由な意思に貼り付いていた「蛇」の情報(偶発的情報)は、自由な意思から引き離されて住処を失い、そのまま焼くために束にされるのである。
イエスは、毒麦のたとえを、弟子たちの望みに応えて次のように解説している。「良い種を蒔く者は人の子、畑は世界、良い種は御国の子ら、毒麦は悪い者の子らである。毒麦を蒔いた敵は悪魔、刈り入れは世の終わりのことで、刈り取る者は天使たちである。毒麦が集められて火で焼かれるように、世の終わりにもそうなるのだ。人の子は天使たちを遣わし、つまずきとなるものすべてと不法を行う者たちとを御国から集めて、燃え盛る炉に投げ入れる。彼らは、そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。その時、正しい人々はその父の国で太陽のように輝く。耳のある者は聞きなさい」(マタイ13,37~43)。「御国」は、生きた人々が集まるミサの空間であり、「世の終わり」とは、ミサの中で、キリストの聖体である主の「羊の囲い」の門が現れるときである。「その父の国で太陽のように輝く」のは、悪霊から解放され、主の「羊の囲い」にその門から入る自由な意思たちである。これらは、聖霊とともに執り行われるミサの中に出現する。そして、その門には「刈り取る天使たち」がいる。
ヨハネの黙示録は、イエスの最期の晩餐がミサに発展した未来を、スケッチした(ヨハネの黙示21,1~27、「神学の河口」№15参照)。「都には高い大きな城壁と十二の門があり、それらの門には十二人の天使がいて、名が刻みつけてあった。イスラエルの子らの十二部族の名であった」(黙示録21,12)、「十二の門は十二の真珠であり、門はそれぞれ一つの真珠でできていた」(黙示録21,21)と書いてある門とは、丸くて白いキリストの聖体を指し、「イスラエルの子らの十二部族の名であった」とは、この門が創世記から始まる契約の歴史の完成であることを表している。12人の天使は、「人々は諸国の民の栄光と誉れとを携えて都に来る。しかし、汚れた者、忌まわしいことや偽りを行う者は誰一人、都に入れない。小羊の命の書に名が書いてある者*だけが入ることができる」(黙示録21,26~27)と書いてあるように、この都に入る者たちを見張っている。そして悪霊を見つけると、「毒麦」と「麦」に分けるのである。このように、ミサに集まって来る者たちは現世の者ばかりではない。イエスが、「私には、この囲いに入っていないほかの羊がいる。その羊をも導かなければならない。その羊も私の声を聞き分ける。こうして、一つの群れ、一人の羊飼いとなる」(ヨハネ10,16)と言ったように、聖霊によって司られているミサには、まさに生きている者も、死んだ者も、すべての人々が招かれている。
*「小羊の命の書に名が書いてある者」という表現は、イエスが、「あなたがたの名が天に書き記されていることを喜びなさい」(ルカ10,20)と応えた言葉、「羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す」(ヨハネ10,3)と言った言葉の「名」と合致する。ここから察すると、人を創造した神は、すべての人に名を付けていた。そして、初めに創造した人アダムに、治めるために他の生き物に名をつけること、しかし名を付けた生き物からは真の助け手を見出せないことを教えた(創世記2,18~20参照)。そこで男となったアダムが、神が彼の助け手として創造した女にエバと名を付けたことは、エデンの園を追われるに相応の行為であった(創世記3,20~24、「神学の河口」№12参照)。
イエスは、ファリサイ派の人々や律法学者たちが、「この人は罪人たちを受け入れ、一緒に食事をしている」と文句を言ったとき、次のたとえを話した。「あなたがたのうちに、百匹の羊を持っている人がいて、その一匹を見失ったとすれば、九十九匹を荒れ野に残して、見失った一匹を見つけ出すまで捜し歩かないだろうか。そして、見つけたら、喜んでその羊を担いで、家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、『見失った羊を見つけましたから、一緒に喜んでください』と言うであろう。言っておくが、このように、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない九十九人の正しい人にまさる喜びが天にある」(ルカ15,4~7)。
このたとえは、イエスが今もミサの中で、「罪人たちを受け入れ、一緒に食事をしている」ことを念頭に置き、ここでこのイエスの言葉を、文字どおり受け取るならば、次のような解釈が可能である。「百匹の羊を持っている人」とは神のことである。「持っている」と言っているところから、この羊たちは、すでに神の手の内にある羊たちであって、現世を生きている者たちではない。さらに「九十九人」について、「悔い改める必要のない正しい人」と言っているところからも、彼らは現世の人ではないと言える。そこで、「九十九匹を荒れ野に残して」と表現したのである。「荒れ野」は死者の世界を表している。「荒れ野に残して」と言われた彼らは、主の「羊の囲い」にすでにいる人々であり、「見失った羊」とは、死んでさ迷う自由な意思や、悪霊となった自由な意思のことである。
イエスは使徒たちに近づいて言った、「私は天と地の一切の権能を授かっている。だから、あなたがたは行って、すべての民を弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼(バプテスマ)を授け、あなたがたに命じたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまで、いつもあなたがたと共にいる」(マタイ28,18~20)。「世の終わり」とは、聖霊とともに執り行われるミサの中に、キリストの聖体が現れる時である。それは、普遍的に広がっていく。ミサの中で、聖霊とともに成すイエス・キリストの救いの継続は、キリストの名で呼ばれるすべてのキリスト者の使命である。キリストの聖体は、「私は世の終わりまで、いつもあなたがたと共にいる」というみ言葉の目に見える実現である。み言葉を聞き、キリストの聖体を、日々、聖霊とともに生み出し、配り、受け取り、見て、触れて、匂いをかぎ、食べるキリスト者たちによって、このみ言葉の実現は継続される(「神学の河口」№15参照)。
すべてのキリスト者が、日々キリストの聖体を受け取って食べることができるために、互いに歩み寄り、その方法を、全力を尽くして模索することは、全キリスト者の緊急課題である。「あなたがたは行って、すべての民を弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼(バプテスマ)を授け、あなたがたに命じたことをすべて守るように教えなさい。」と言ったイエスの命令の保証が、「私は世の終わりまで、いつもあなたがたと共にいる」という言葉にある、すなわち、キリストの聖体にあるからである。
つづく
2020年7月 広島にて
Maria K
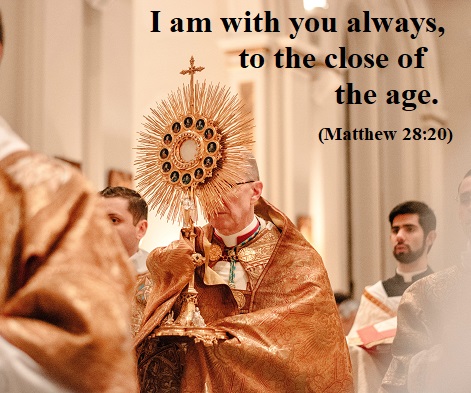
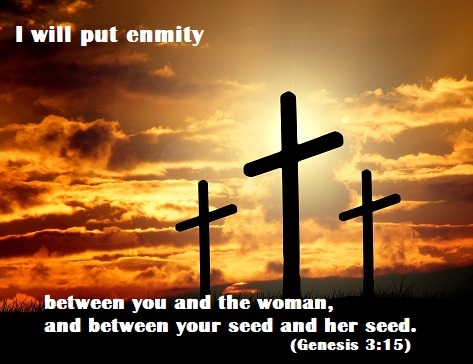
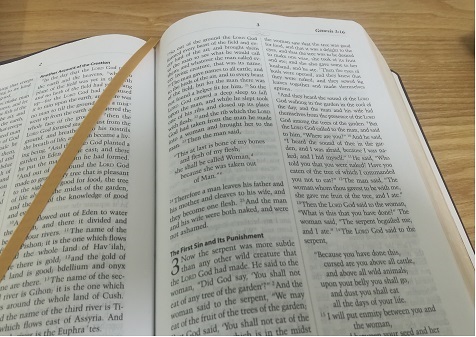
コメント
コメントを投稿